|
2. 主人公の秀二は、シネマを救おうとしている、 |
1 | 2 | 3 |

Q:今回、『サウンド・バリア』(05)と『ベガス』(08)と『CUT』を拝見させて頂いて、どれも凄く面白かったのですが、スタイルがそれぞれ違って、『サウンド・バリア』はかなり実験的なスタイルでしたが、『ベガス』はハリウッドのオーソドックスな映画言語を用いていました。今回の『CUT』は映画のスタイルという意味で、どういう風に撮ってみようとお考えだったのか、お聞かせ頂けますか?
AN:今回の『CUT』もどちらかというと『サウンド・バリア』に近いのかなと自分では思っています。何かを証明したいと思っている、凄く執着している主人公が登場しているという共通点、『サウンド・バリア』を作ったおかげで『CUT』ができたような、そういう関係性があります。編集であったり、沈黙の使い方であったり、音の使い方であったり、なにか『サウンド・バリア』を作ったことによって『CUT』を作る準備が出来たという、そういう位置づけですね。

『ベガス』もご覧になってらっしゃるということで、『ベガス』はまた全然違って、あれは自分のアメリカでの作品作りの集大成といえるような作品です。いつも自分にとって他の国で映画を作るということは、その国の人のようにその国の映画を作る、彼らのその文化、彼らのテーマを掘り下げて作るということが自分にとっての挑戦なわけで、それをアメリカでやったわけです。自分にとっては『べガス』はだからジョン・フォード、ジョージ・スティーヴンス、ドン・シーゲルといったアメリカの巨匠と言われている人々のスタイルを踏襲したような作品です。だからまず登場するキャラクターも<風景>、ランドスケープなんですよね、アメリカは基本的にあんなに大きい国なので、どこを撮ってもまずランドスケープからという感じになるわけです。人の表現というのも外向きの表現、感情表現が大きいですけど、みんないつも叫んでるような感じです。日本はそうではなくて、もっと内に向かってのエネルギーがある、シャドーピープルといつも私は言っていますが、どちらかというと陰と陽だったら陰の方の、そういう性質があると思っているんです。
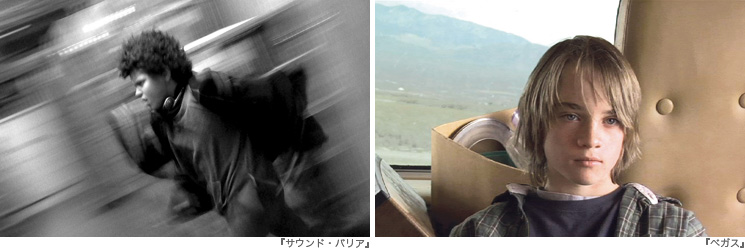
例えば、20年位前の私のインタヴューを読んで頂いても、日本で自分の映画を作りたいなんてことをずっと言っていたんです。急に言い出した訳ではなく、いつもそう言っていたんです!それは日本の映画を教える立場から見ていて、日本映画を外国人の監督が撮った時に、決して日本映画になりきれてないというところをずっとはがゆい思いで見ていたからなんです。自分が作るならば1から100まで、AからZまで日本映画というものを作りたいと、ただのロケーションとして日本で撮りましたという観光映画ではないものを作りたいと思っていて、なので今回は“ジム”という場所に日本人的資質、キャラクター、人物、そういったもの全て入れ込んで、これが日本だと言えるそういう設定で作っているのです。屋外に出てもいわゆるネオンであったり、銀座であったり、観光で行くようなありきたりの日本的な映像というのは一切出てきません。だからスタイルとしては、自分が思う日本のハートを自分が感じ取りながら、ちょっとした木目、テクスチャーであったり、感じというのを映像化した、それは正に『サウンド・バリア』の時と同じなんですね。

自分はだから一本ずつ次の作品を思いながら映画作りをしています。どんな作品でも自分の主人公ですから一緒なんですね。何かに執着心を燃やし、何かを証明しようと、そして常にリミットの限界を最後までギリギリまでどこまで行けるか挑戦してるようなところがある、自分の気持ちにとても正直で、その何かを得る為に対価を払わなければいけない、そういったキャラクター、『ベガス』の場合はちょっとクレイジーだったけれども『サウンド・バリア』でも同じようなキャラクターが出て来るし、『CUT』の場合はもちろん西島さん演じるキャラクターというのがシネマを救おうとしている、その為には自分の体でその対価を払わなければいけないと彼は思っている。だからキャラクターはその言葉、文化、舞台が違っても自分の場合は同じ、究極的には結局それは人間だからです。

数日前に『サウンド・バリア』を上映した時に、黒沢清監督がコメントをして下さって、外国人が撮った映画とは思えません、非常に驚かされました、と言って下さったんですね。凄く誇らしく思ったし、黒沢監督のような本当に純粋な映画作家と呼べる方がそういう風に言ってくれるということがやはりとても嬉しかった。自分がさっき言ったように『CUT』は自分のハートで感じたことを映像化している、それを多分ハートで感じてもらっているんだなと凄く感じました、自分にとってはとても重要なことなのでとても嬉しかったのです。

『ベガス』もご覧になってらっしゃるということで、『ベガス』はまた全然違って、あれは自分のアメリカでの作品作りの集大成といえるような作品です。いつも自分にとって他の国で映画を作るということは、その国の人のようにその国の映画を作る、彼らのその文化、彼らのテーマを掘り下げて作るということが自分にとっての挑戦なわけで、それをアメリカでやったわけです。自分にとっては『べガス』はだからジョン・フォード、ジョージ・スティーヴンス、ドン・シーゲルといったアメリカの巨匠と言われている人々のスタイルを踏襲したような作品です。だからまず登場するキャラクターも<風景>、ランドスケープなんですよね、アメリカは基本的にあんなに大きい国なので、どこを撮ってもまずランドスケープからという感じになるわけです。人の表現というのも外向きの表現、感情表現が大きいですけど、みんないつも叫んでるような感じです。日本はそうではなくて、もっと内に向かってのエネルギーがある、シャドーピープルといつも私は言っていますが、どちらかというと陰と陽だったら陰の方の、そういう性質があると思っているんです。
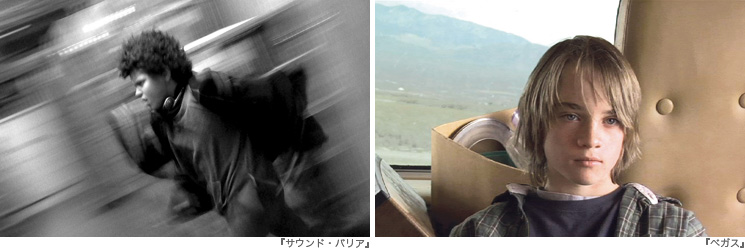
例えば、20年位前の私のインタヴューを読んで頂いても、日本で自分の映画を作りたいなんてことをずっと言っていたんです。急に言い出した訳ではなく、いつもそう言っていたんです!それは日本の映画を教える立場から見ていて、日本映画を外国人の監督が撮った時に、決して日本映画になりきれてないというところをずっとはがゆい思いで見ていたからなんです。自分が作るならば1から100まで、AからZまで日本映画というものを作りたいと、ただのロケーションとして日本で撮りましたという観光映画ではないものを作りたいと思っていて、なので今回は“ジム”という場所に日本人的資質、キャラクター、人物、そういったもの全て入れ込んで、これが日本だと言えるそういう設定で作っているのです。屋外に出てもいわゆるネオンであったり、銀座であったり、観光で行くようなありきたりの日本的な映像というのは一切出てきません。だからスタイルとしては、自分が思う日本のハートを自分が感じ取りながら、ちょっとした木目、テクスチャーであったり、感じというのを映像化した、それは正に『サウンド・バリア』の時と同じなんですね。
自分はだから一本ずつ次の作品を思いながら映画作りをしています。どんな作品でも自分の主人公ですから一緒なんですね。何かに執着心を燃やし、何かを証明しようと、そして常にリミットの限界を最後までギリギリまでどこまで行けるか挑戦してるようなところがある、自分の気持ちにとても正直で、その何かを得る為に対価を払わなければいけない、そういったキャラクター、『ベガス』の場合はちょっとクレイジーだったけれども『サウンド・バリア』でも同じようなキャラクターが出て来るし、『CUT』の場合はもちろん西島さん演じるキャラクターというのがシネマを救おうとしている、その為には自分の体でその対価を払わなければいけないと彼は思っている。だからキャラクターはその言葉、文化、舞台が違っても自分の場合は同じ、究極的には結局それは人間だからです。
数日前に『サウンド・バリア』を上映した時に、黒沢清監督がコメントをして下さって、外国人が撮った映画とは思えません、非常に驚かされました、と言って下さったんですね。凄く誇らしく思ったし、黒沢監督のような本当に純粋な映画作家と呼べる方がそういう風に言ってくれるということがやはりとても嬉しかった。自分がさっき言ったように『CUT』は自分のハートで感じたことを映像化している、それを多分ハートで感じてもらっているんだなと凄く感じました、自分にとってはとても重要なことなのでとても嬉しかったのです。

| 1 | 2 | 3 | |
