日本公開新作映画ベスト10
イーデン・コーキル
今年、映画館でもっとも面白い体験をさせてくれた作品は、松本人志の手によるものだった。簡単に言ってしまえば、テレビのお笑い芸人として長いキャリアを持つ松本の監督二作目(2007年の『大日本人』に続く)『しんぼる』はこれまで見たことのないタイプの映画だ。
あるレベルでは完全に超現実的で、パジャマに身を包んだ松本本人が扮する主人公が、真白い部屋で、時折壁のレリーフとして浮き出る天使たちの陰茎を押しながら無作為に「歯ブラシ」のような物を与えられ、ウロウロするだけでフィルムの半分が費やされる。しかし、物語が進むにつれ、奇天烈ではあるけれど、このパジャマ姿の主人公がなんと「神」(?)へと昇格する存在であり、我々が見せられているエピソードがその修業過程であることが明かされていく。奇怪に聞こえるだろうが、映画終盤になると、世界各国の気象からオバマの当選まで、この世の森羅万象に関して、決定権を握っているのは、このパジャマを着た松本なのである。 松本は『大日本人』で、目玉も飛び出るほど独創性に溢れるストーリーと突飛なユーモアを巧みに調合する能力を見せた。今回はそれに、息をのむほど美しいプロダクション・デザインという引き出しが加わった。神格的なキャラクターをビジュアル化する試みが危険であるのは周知の事実。しかし『しんぼる』は、奇天烈さに劣らず映像美を誇る作品に仕上がっている。 2位に入れた『チェンジリング』は2009年一番のサプライズだ。 息子が失踪した後、別の子供を返される女(アンジェリーナ・ジョリー)の物語と聞いた段階で、私のセンチメンタル探知機の針は振り切っており、妻にどうしても行きたいとねだられなければ映画館に行く事すら拒んだだろう。 だが、監督のクリント・イーストウッドを信じるべきだった。母親の訴える内容の信憑性を深める証拠を早い段階に映し出すことによって、不当行為を暴く物語を誠実にストレートに描く、というのがイーストウッドの絶好なアプローチだった。 更なる彼の熟練の業は、途中から本当の息子が生きているかどうか、というクエスチョンに焦点を移行するところにある。気がつけば、息子の死を示唆する証拠が積みあがっていくにも関わらず、希望を無くすまいと必死に子供の生存を信じる母親に肩入れするという、言ってみればセンチメンタルな感情に飲み込まれそうな自分がいた。 ジェームズ・マンゴールドの『3時10分、決断のとき』は、正真正銘の西部劇でありながら、観終わった瞬間からもう一度観たくなる、というくらい面白い作品である。 二人の主役、ラッセル・クロウとクリスチャン・ベイルが始めから終わりまで物語に良い緊張感を与えているが、それは単に二人の間に交わされる敵対行為や台詞からくるわけではない。むしろ、その緊張感を最後まで保たせるのは、二人がお互いのことをどう思っているのか、敵なのか?表裏一体の運命共同体なのか?が明かされないことである。 クエンティン・タランティーノは、静かに、じっくりと時を刻む脅威が突如暴力へと傾きだす描写において他の追随を許さない達人である。 『イングロリアス・バスターズ』に彼を駆り立てたのは、映画を通してナチに制裁を加えたいという欲望だったのは明らかだ。史実に基づくかどうかは別として、タランティーノに料理された悪党たちは全員グロリアス!だ。ディーター・ヘルストロム少佐(アウグスト・ディール)は酒場のゲームを尋問に流用しながらも微笑みを絶やさないし、ハンス・ランダ大佐(クリストフ・ヴァルツ)に至っては、あまりの怖さに、ミルクを飲む場面だけで鳥肌が立つ程だった。 オーストラリア人であるならば、バズ・ラーマンの『オーストラリア』を高く評価するのではないかと思う。その一人である私にとって、この映画は喜ばしい出来映えだ。なぜなら、大衆文化におけるオーストラリア版「國民の創生」を大きなスケールで描こうとする試みが余りにも少ないから。 ラーマンは、オーストラリアにおける牧畜王同士の確執から英国への憧憬、「盗まれた世代」の先住民アボリジニ、そして日本軍のダーウィン島襲撃まで、数多くの要素をこの映画に詰め込んだ。やり過ぎだと感じる方もいるかもしれないが、これらが全て前世紀の前半にオーストラリア北部で実際に起きた出来事だということは、オーストラリア人であれば誰しもが知っている。 この数多くの要素全てが整合し、共振し合い、そして全体として素晴らしいフィルムを構成している。 ドキュメンタリー『花と兵隊』で、監督の松林要樹が太平洋戦争の退役軍人である87歳の日本人に、当時隊員は人肉を食べたという噂について訊くシーンがある。老人の返答よりも興味深いのは、30歳の松林が、こんな質問をするのにぎこちない作り笑いともつかない曖昧な表情を浮かべていることだ。 この1ショットのイメージが、『花と兵隊』の神髄である世代の衝突を捉えている。日本の若い世代は、彼らの祖父母世代が経験した恐怖について何も知らないばかりか、それを聞き出す機会も術もないのであろうか。 アメリカ人が、ヨーロッパ(若しくはエキゾチックな異国など)を旅して初めて、自分の中に潜むロマンチックで創造的な側面を発見するというシナリオにはうんざりだが、ウディ・アレンの『それでも恋するバルセロナ』ではその様子が余りにも大げさに描かれているため、ある種のパロディとして成功している。また、この映画は近年稀にみる健やかな官能性に満ちた映画でもある。 私は、いわゆる「白人救世主」という概念を不快に思う部類の人間だ。『ラストサムライ』で、米国から訪問した白人のトム・クルーズがサムライ魂を会得したのに疑問を覚えたし、『アバター』で白人のジェイク・サリー(サム・ワーシントン)が先住民族ナヴィ軍を率いて戦争に勝つのも鼻についた。 逆に楽しめた点は、ジェームズ・キャメロン監督の視点の広さだ。パンドラという惑星を生み出した想像力や、人間がエイリアン、アバターの身体を借りられるという驚きの発想。アクションのシークエンスにも興奮させられた。 先住民族を率いたのがナヴィ族のツーテイでさえあれば良かったのだが。 際立ってスタイリッシュな『パブリック・エネミーズ』で、強烈な印象を残すのは、ジョン・デリンジャー(ジョニー・デップ)が、恋人(マリオン・コティヤール)、もしくはデリンジャーを追跡するFBIエージェント、メルヴィン・パーヴィス(クリスチャン・ベイル)と正面から対峙する姿勢だ。残念なのはどちらも十分な時間的な長さで描かれていないこと。監督のマイケル・マンには、特にデップとベイルの対比をもっと見せて欲しかった。 『グラン・トリノ』は、最後のシーンまでは、とても楽しめた。監督のクリント・イーストウッドは絶妙な緊張感をもってフィルムを構成している。 ただ私には、クライマックスの(次の文章でネタを明かしてしまうが)辻褄が合っていないように思えてならない。ウォルト・コワルスキー(イーストウッド)は、モン族のギャングが刑務所に長期拘留されるだろうという勘を頼りに人生を犠牲にした。だが、果たしてそうなのか?私は弁護士ではないが、日頃から銃を振り回しているという噂のある朝鮮戦争の退役軍人が夜中に家の前に現れたとあれば、被告も「安全を脅かされた」として正当防衛を主張出来るのではないか? もしそうなれば、コワルスキーの犠牲は何の役にも立たない。杞憂かもしれないが、どうもこの疑問が頭に引っかかってならない。 日本公開新作映画ベスト10
鍛冶紀子 『母なる証明』ポン・ジュノ
あのオープニングシーンとラストシーンは、後々映画史で語られるのではないかと思う。09年の映画で最も観るのにエネルギーを要した作品だった。観賞後どっと疲れて思わず深いため息が。脚本も演出も音楽もキャスティングも見事。ポン・ジュノはもちろん天賦の才を持つのだろうが、それのみに頼らず映画をしっかり学んでいる様子が端々に伺える。それゆえにつくり得た傑作なのだと思う。とにかく圧巻。
『ぼくら、20世紀の子供たち』ヴィターリ・カネフスキー
「2009年日本公開」の冠にはそぐわないかもしれないが、個人的にはようやく観ることができたので選ばせてもらった。ソ連崩壊後の混乱した社会の中で、たくましく且つ鋭く生きざるを得ない子供たちをニュートラルに撮った傑作。過酷な中で時折見せる子供たちの“子供らしさ”が胸にささる。
『懺悔』テンギス・アブラゼ
こちらも「2009年日本公開」の冠にはそぐわないかもしれないが、1月に岩波ホールで観た際、強烈なインパクトがあったのでぜひ挙げておきたい。独裁者の市長ヴェルラム(明らかに彼の独裁者たちをカリカチュアしたキャラクター)と、彼によって両親を粛清された女性ケテヴァンを中心に話は進む。スターリンとベリアという二人の冷酷な独裁者を生んだ自国(グルジア)に対する自戒を込めたとも取れるタイトルに、監督の想いの一端を見たように思う。
『愛のむきだし』園子温
ハチャメチャでおかしくて悲しくて痛い、圧倒的な237分だった。笑いはやがて感動になり、四時間後にはある種のカタルシスさえ感じていた。主演の西島隆弘、満島ひかり、安藤サクラがすばらしい。ラヴェルとゆらゆら帝国とベートーヴェンとサン・サーンスを並列にかけるセンスにも脱帽。
いわゆるフェミニズムとは一線を画すアニエスの神髄を見ることができた作品。ジャック・ドゥミへの深い愛には胸が熱くなった。また、そのファッションや色彩感覚に、本物の「かわいい」とはこういうものだ!とほれぼれ。
『我が至上の愛—アストレとセラドン—』エリック・ロメール
暗い空気を感じざるを得なかった2009年。そんな閉そく感とは無縁に美しき世界に陶酔する幸せを与えてくれた本作。偽りが横行する現代に於いて、ロメールの忠実さは戒めにすら見える。ああ、ロメールよ!本当にこれで最後なのですか?
レビューにも書かせていただいたが、オルミの問いかけは今後ますます重みを増していくだろう。「私たちをより優れた人間にしてくれるものが良心の奥底でわが身に問うことを可能にする勇気である」オルミのこの言葉とともに、深く広く議論されていくことを願うばかり。
『ピリペンコさんの手づくり潜水艦』ヤン・ヒンリック・ドレーフス、レネー・ハルダー
ピリペンコさんという人が、ピリペンコさんのような人が、この世にいることを教えてくれたことに感謝。スクリーンに写るウクライナの小さな村では、時間の流れも人や動物の在り方も物の価値観も、東京に住む我々とは全く違っていて、生きる=暮らすということについてしみじみ考えさせられた。
『ウォッチメン』ザック・スナイダー
正義の名の元に振りかざされる悪。1980代年の舞台設定だが、同時に2000年代の縮図でもある。ハリウッドらしいエンターテイメント性を多分に含みつつ、「誰が見張りを見張るのか?」という自国への批判性も忘れなかった。後半の失速は残念だったが、観賞後それなりの満足感があった。原作を忠実に映画化したのが功を奏したか。
『THIS IS IT』ケニー・オルテガ
マイケル・ジャクソンはつくづく映像の人だと思う。生前も、そして死後も、彼は映像の中で輝いた。それは良きにつけ悪しきにつけ常にエンターテイメントとして消費される。本作は映画としての出来不出来を問われる類いのものではなく、只々彼を悼み、惜しみ、愛するための映像であったと思う。彼の囁くような「I love you. Got bless you.」が忘れられない。
日本公開新作映画ベスト10
浅井学 1.『チェ 28歳の革命|39歳別れの手紙』スティーヴン・ソダーバーグ
木々と硝煙の匂い。キューバ革命前夜、若き日の希望と活気に満ちあふれたシエラ・マエストラ山の野営地。そして、晩年の孤立無援、追いつめられ絶望感漂うボリビアのアンデス山中。まさに、革命か死か!ゲバラの革命人生における明暗のコントラストを飾ることなく淡々と見せてくれた。ゲバラの足跡をたどるためキューバを訪れた者として思い入れの強い作品。
2.『太陽のかけら』ガエル・ガルシア・ベルナル
『チェ 28歳の革命|39歳別れの手紙』のプロローグとも言える『モーターサイクル・ダイアリーズ』(ウォルター・サレス/04)で若き日のゲバラを演じたガエル・ガルシア・ベルナルの初監督作品。メキシコの上流階級の若者たちが集う郊外の別荘での夏の1日。流れないトイレ、幼なじみでもある使用人との確執、アメリカの大学からの不合格通知、世界的不況下で金策にかけまわるようになった親、悪のりした妹は薬物の過剰摂取で….全てがちょっとずつ壊れていく。メキシコのコントラストの強烈な独特な空と緑が美しく印象的だ。
3.『愛のむきだし』園子温
約4時間の長編だが怒濤の展開と独特な世界観にひきつけられた。盗撮集団、パンチラ、カルト教団、コスプレ、トラウマ…とわかりやすいアイテムがちりばめられる中、単なるサブカル映画に終わらない。エンディングの瞬間に「面白かった!」と久方ぶりにひとりごちた。次回作も含めその活動が大いに気になる監督。
4.『レスラー』ダーレン・アロノフスキー
俳優として言わば“過去の人”であった主演ミッキー.ロークの復活劇というサイドストーリーも相まってこの映画を一層感動的なものとしている。
5.『チェイサー』ナ・ホンジン
『羊たちの沈黙』の緊迫感と『24』並のテンポで事件が錯綜する、息つく間もない極上のエンターテインメント。ヒューマンドラマとしての完成度も高い優れた作品。
6.『グラン・トリノ』クリント・イーストウッド
勝手に『ダーティー・ハリー』の孤高の刑事ハリー・キャラハンのその後の物語として見た。いわば、アメリカの良心。
7.『ウォッチメン』ザック・スナイダー
輝かしいアメリカ現代史を彩ったスーパーヒーローの抱える、苦悩にみちた哲学的ともいえる物語。いわば、アメリカのダークサイド。
8.『ミルク』ガス・ヴァン・サント
ゲイの権利運動のアイコン、殉教者、ハーヴェイ・ミルクという人物をはじめて知った。70年代の西海岸のゲイコミニティの空気と日常がリアルに描かれている。やはりショーン・ペンは素晴らしい俳優だ。
9.『ヱヴァンゲリヲン:破』庵野秀明
リメイクながら新たな登場人物、エヴァンゲリオン、使徒が登場するなど、エヴァの世界観を再構築しながら、ストーリーと謎はさらに分離拡散しはじめる。こうなると、やはり追いかけざるを得ない。
10.『サマーウォーズ』細田守
村上隆のルイ・ヴィトンの店頭プロモーション用アニメ『SUPERFLAT MONOGRAM』、『時をかける少女』など間違いなく見ておくべきアニメ監督。
日本公開新作映画ベスト10
上原輝樹
私にとって、2009年は、上位3作(タランティーノ、マン、ジャームッシュ)のアメリカ映画とイーストウッドの2作品に代表される1年だった。イーストウッドは、あまりにも素晴らしく決まり過ぎた『グラン・トリノ』よりも、いい知れぬ後味の悪さがいつまでもつきまとう『チェンジリング』を選んだ。2月に公開される新作『インヴィクタス』は、『グラン・トリノ』で示された決意を明確に受け継ぐ、新たに始まる10年<New Decade>への希望に満ちたメッセージを明確に発している傑作であり、その『インヴィクタス』の誕生は、『グラン・トリノ』における自らの半生の総括から生じたものに違いないとはいえ、そのような映画史的要請はさておき、自らの好みに準じて異形の傑作『チェンジリング』の方を選んだ。
そして、こと“東京”に関して言えば、2009年は、オリヴィエ・アサイヤス、イエジー・スコリモフスキ、アニエス・ヴァルダの年であったことも忘れない。彼らの過去の作品を、特集上映の機会にスクリーンで見ることが出来たのは素晴らしい体験だったし、いずれも素晴らしい新作を届けてくれた。特に、アサイヤスの『夏時間の庭』は、『感傷的な運命』を現代に引き継ぎ、変わるもの/変わらないものというテーマの深化と同時に、未来への瑞々しい希望の光で夏の緑を煌めかせる、アサイヤスの新境地を切り開いた傑作だった。 ほぼ時を同じくして、エリア・スレイマンの『時の彼方へ』とアモス・ギタイの『カルメル』が映画祭で上映された。両作品とも、自らの家族の歴史というプライベートな記憶と体験を通じて、パレスチナとイスラエルの歴史を描いた作品。『時の彼方へ』は、パレスチナ人の視点から、『カルメル』はイスラエル人の視点から描かれ、どちらの作品も、困難な状況にありながらも、人生の豊かさへの憧憬がフィルムに美しく刻印されているところが素晴らしかったが、2009年の冒頭、建国50年を迎えたイスラエルは、ガザ地区への攻撃を強める一方、“侵略行為”のイメージを薄めるため、文化政策の一環として“映画”でイスラエルの文化を世界に伝える試みが積極的に採用された事に対して、明確に批判的なスタンスを持つイスラエルの映画作家アヴィ・モグラビの特集上映は、とても興味深いものだったが、アモス・ギタイの作品には、美しい締念のようなものが漂っていて、非常に複雑な感情を覚えた。ペドロ・コスタが語ったように、“映画は常に政治的なもの”であらざるをえないのだから。 『母なる証明』のポン・ジュノは、間違いなく、今、アジアで随一のスケール感を誇る映画作家だと思う。残念ながら、日本映画はあまり多くの作品を見ることができなかったこともあり、このレベルに達する作品に出会えなかったが、松村浩行の『TOCHKA』はひときわ異彩を放ち、今年見たどの他の映画にも似ず、むしろ池田亮司の音楽やアートワークに匹敵する物質的強度を持った希有な作品だった。 チャーリー・カウフマンの『脳内ニューヨーク』は驚くべき問題作だったが、かなり混乱した作品であるにも関わらず、見終わってしばらくすると、もう一度見たくなるという本当に困った作品だった。一度も見なければ、このような苦悩とも無縁でいられるのだが、、、。この作品の無謀さも含めて、やはり、ここまでやってしまうか!と驚かせてくれたのは、タランティーノの『イングロリアス・バスターズ』にしろ、ジャームッシュの『リミッツ・オブ・コントロール』にしろ、いずれもアメリカの映画作家だったという2009年だったように思う。 その他に、ベスト10からは便宜上もれたものの、特記しておきたいのが以下の作品。 『ダウト』ジョン・パトリック・シャンリー 卓越した脚本と演出、素晴らしい俳優陣(メリル・ストリープ、フィリップ・シーモア・ホフマン、エイミー・アダムス)のアンサンブルが光る。 『ずっとあなたを愛してる』フィリップ・クローデル 今どき珍しい、監督の誠実な人柄が作品に滲み出た傑作。有名小説家の第一回映画監督作品。 『春風沈酔の夜』ロウ・イエ FILMEXで上映。『天安門、恋人たち』ロウ・イエの新作。素晴らしく息の長い演出で、人の生命を蓮の花の短い一生に喩える郁達夫の詩を引用しながら、個人が抑圧される中国という国で、男女5人が複雑な恋愛に傷つき苦しみながらも、それでも最後には一瞬の夢心地な時間に“希望”を託し、人間の幸福とは何か、愛、そして生きることの輝きを陽炎のように儚く揺れる時間の中で捉えた傑作人間ドラマ。 日本公開新作映画ベスト10
VALERIA 小倉聖子 1位:『THIS IS IT』ケニー・オルテガ
マイケルのムーンウォークがこんなにもすごいものだったのかと思えたのと、マイケルの人柄が全面に出ていたところが素晴らしかった。リハの途中で観客席で見ていたバックダンサーにのせられ本気を出して歌ってしまうマイケルが「あまりのせないでくれよ」と言うシーン、そしてその歌の後に観客席にカメラを向けるとそこは何万人もいる観客ではなく12,3人のダンサー達がウォー!とかフォー!とか、盛り上がっているシーンなど、マイケルの周囲の人間の感動が私たち観客にまでストレートに伝わってくる映画。
初めの10分間ホラー映画が始まったかのような緊張感から、突然川に流れて来る牛の死骸に“ハッと”させられ、わけもわからない笑いがこみ上げてくる。その後、また緊張感が続き、絵画のように美しいシーンの異様さにまた “ハッと”させられ、ヘリコプターの音が尋常じゃない大きさで響き、最後には感動と驚きに襲われる95分間。久しぶりに観た映画らしい映画。
3位:『愛を読むひと』スティーヴン・ダルトリー
原作を全く読まずに観た映画だったが、久しぶりに上映終了後も映画館の席から立ち上がることができなかった。自転車を一緒に乗って出かけるシーン、カセットテープに吹き込むシーン、全てがステキ。少年が最後まで1人の女性しか本気で愛せなかったせつなさが心の中にじんわりと響いた。ロジャー・ディーキンスとクリス・メンゲスという2人の撮影監督の仕事も見事。
4位:『イースタン・プレイ』カメン・カレフ
主演のフリスト・フリストフの演技ではない演技が、胸に響いた。ブルガリアの何もない遠い空と大地、そして光がフリストと融合する街のシーンがすごく神秘的。映画の撮影後に亡くなってしまったフリストフのまなざしや、背中、指、を見ているだけで鳥肌が立つ。不安な社会情勢が続くブルガリアで自分の生きる道を探す兄弟を描いた素晴らしい人間ドラマ。
5位:『THIS IS ENGLAND』シェーン・メドウズ
80年代前半のイングランド・ミッドランド地方。監督の少年時代を描いた作品。ファッション、音楽、脚本、映像、全てにおいて本当に良く出来た久しぶりのイギリス映画だった。イギリスの労働者階級の少年の感情を中心に、国に対して思うこと、将来への不安などをリアルに描いた名作。楽曲の選出も素晴らしい。
6位:『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』デイヴィッド・フィンチャー
ケイト・ウィンスレットとブラット・ピットの名演技と美貌に終始目を奪われた。人の人生を逆から描くと、一緒に居る大切な人と共有できる時間の限りある切なさがひしひしと伝わってくる。フィンチャー映画らしい、綿密なディテールのひとつひとつが嬉しい。ブラッド・ピットの若い頃の映像に、単純にかっこいい!と感動してしまった。
7位:『レイチェルの結婚』ジョナサン・デミ
アン・ハサウェイがダメな妹役を好演していたところも良かったが、手持ちカメラから臨場感が伝わってくるジョナサン・デミの映像にセンスを感じた。インド人と結婚することになっている姉、その結婚式で流れる音楽も素晴らしい。シンプルな映画だが、姉と妹の心理をよく描いた、シドニー・ルメットの娘ジェニー・ルメットの脚本も良かったと思う。
8位:『スペル』サム・ライミ
単純に、恐くて、笑えて、笑えて、、、気づくと笑っている方が長い作品だった。ジプシーの婆さんの呪い、そしてミス豚肉という称号を過去に持つヒロインのクリスティン。婆さんとクリスティンの戦いがおもしろいくらいよく出来ていて、最後の「あーー!」というどんでん返しまでたっぷりと楽しませてもらえる作品。
9位:『スラム・ドック$ミリオネア』ダニー・ボイル
インド人の目線が反映されいる視点と、最後のうなるような展開に納得!の1本。
10位:『マンマ・ミーア!』フィリダ・ロイド
ギリシャの美しい景色とABBAの音楽が見事に融合されたミュージカル映画。メリルの娘役のアマンダがあまりにも可愛いく、スタイル抜群なところに同性ながらも目を大いに奪われた。女性だったら誰でも楽しめるミュージカル映画に仕上がっている。
|
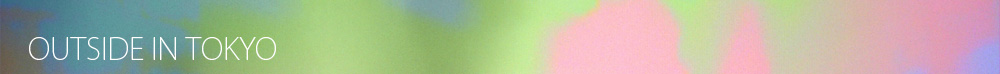 |
|